
6月23日は、第二次世界大戦の沖縄戦で犠牲になった人たちをしのんで平和を願う「慰霊の日」。沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦いが終わったとされる日でもあります。約20万人が犠牲になった沖縄戦とは何だったのでしょうか。【真田祐里】
第二次世界大戦末期、圧倒的な兵力のアメリカ軍を前に、日本は国内で戦う「本土決戦」に備えました。アメリカ軍が日本の本土(本州、九州など)に上陸するのを遅らせるため、沖縄を「捨て石(大きな目標のために見捨ててしまう犠牲)」とする作戦を取ったのです。
アメリカ軍は1945年3月26日、沖縄本島の西に浮かぶ慶良間諸島へ、4月1日には沖縄本島に上陸しました。ここから約3か月におよぶ沖縄戦が始まります。アメリカ軍の砲撃は地形が変わってしまうほどすさまじく、「鉄の暴風」と呼ばれました。
沖縄県の調べでは、沖縄戦ではアメリカ兵も含めて約20万人が亡くなりました。このうち沖縄出身者は、半数を超える約12万人です。しかも、その7割以上にあたる約9万4000人が、軍人ではなく住民でした。当時の沖縄県民は約50万人だったので、4人に1人が犠牲になったことになります。
なぜこれほど多くの住民が犠牲になったのでしょうか。
日本軍は、足りない兵力を補うために10代の子どもを含む住民も戦闘に参加させました。また、多くの住民が「ガマ」と呼ばれる洞窟に隠れていましたが、後から来た日本軍に追い出されて亡くなったり、アメリカ軍のスパイ(協力者)と間違われて殺されたりしました。さらに、アメリカ軍に捕まるのを恐れたり、日本軍に強制されたりして、家族や近所の人たちが集団で命を絶つ「集団自決」も起きてしまったのです。
住民を巻き込んだ激戦の末、本島の南に追い詰められた日本軍は、6月23日に牛島満司令官が自決し、組織的な戦闘は終わりました。その後、沖縄はアメリカに支配されました。
沖縄は72年5月15日に日本へ復帰しましたが、今もなお、日本のアメリカ軍関連施設の7割が沖縄にあり、他の地域と比べて重い負担を背負っています。=2面につづく
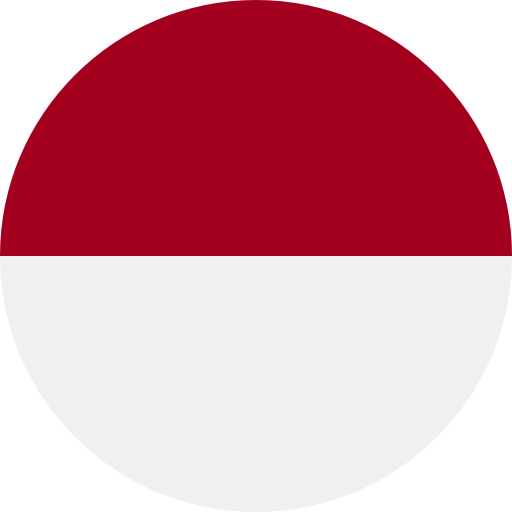 Indonesian
Indonesian
 English
English
 Hindi
Hindi
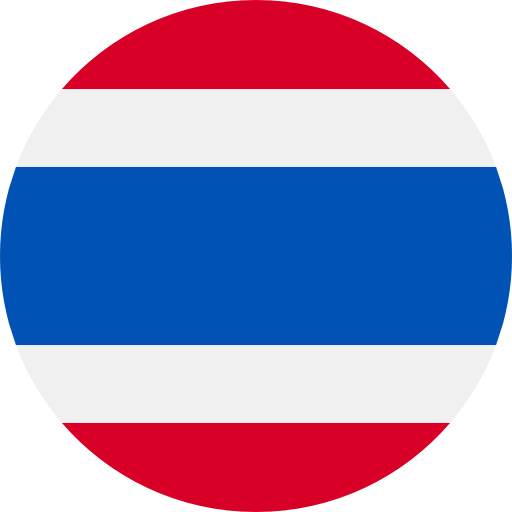 Thai
Thai
 Vietnamese
Vietnamese
 Burmese
Burmese
 Spanish
Spanish
 Portuguese
Portuguese
 Arabic
Arabic
 Russian
Russian
 Chinese
Chinese

