
日本に暮らす外国人に災害の備えを――。在留外国人の数は2024年6月末時点で358万8956人です。10年ほど前(14年12月末)に比べ約1・7倍に増えています。こうした人たちが生活していく上で欠かせない災害対策を手助けしようと、各自治体はシンプルで分かりやすい「やさしい日本語」を使い防災セミナーを開いています。どんなものなのか取材しました。【田後真里】
福岡県は21年度から市町村と協力して、居住する外国人対象の防災講座を開いています。
特に24年度は、国籍などが共通するコミュニティーの代表者らへの情報提供に力を入れました。代表者らが身につけた防災の知識を、コミュニティーに戻って仲間と共有してもらうのが狙いです。
2月初旬に福岡県北九州市であったセミナーには、市内のベトナム人協会やイスラム文化圏のグループから9人が参加しました。
「緊急地震速報は『これから地震で大きくゆれます』という意味です」。講師で加わった気象庁・福岡管区気象台の職員は、災害時の映像や写真とともに、防災関連の用語や意味を、わかりやすく説明しました。そして、防災対策に役立つアプリを紹介しました。
出身国や地域によって、自然災害の知識には大きな差があります。セミナーではVR(仮想現実)ゴーグルを使い、参加者らが地震や大雨を疑似体験しました。途中、参加者が驚いて叫ぶ場面もあり、「水位が急に上がるところがリアルで怖かった」などと感想が聞かれました。
中国の遼寧省出身の金枝さん(37)は小学1年の長女らと参加しました。外国人の保護者仲間には、日本語がほとんど話せない人もいるといいます。「まずは(防災対策をまとめた)冊子やホームページの存在を伝えたい」と話しました。
身近に暮らす外国人に対して、市民レベルでできるサポートもあります。セミナーを主催した福岡県国際交流センターの国際交流専門員、明珍奨真さん(31)は、いろいろな言語に対応した自治体の資料やアプリの案内▽気象庁の防災情報で使われる危険度を示す5段階の色分けや、避難指示の意味を伝える▽「ひなんじょ」の言葉や存在を知らせる――などを提案しています。
明珍さんは「災害時に特有の言葉の表現や避難所の機能などをできるだけ多くの人に事前に伝えることが、速やかな避難につながります」と呼び掛けました。
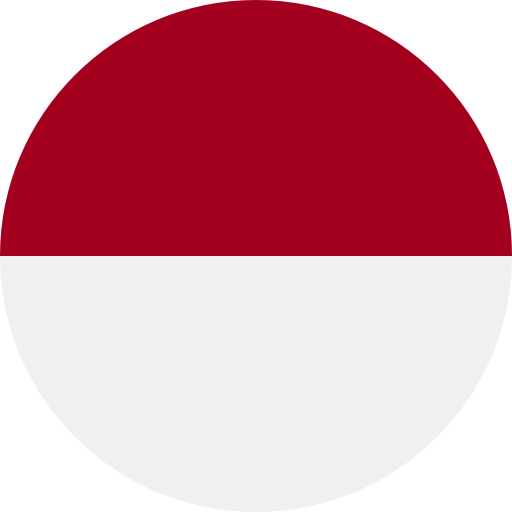 Indonesian
Indonesian
 English
English
 Hindi
Hindi
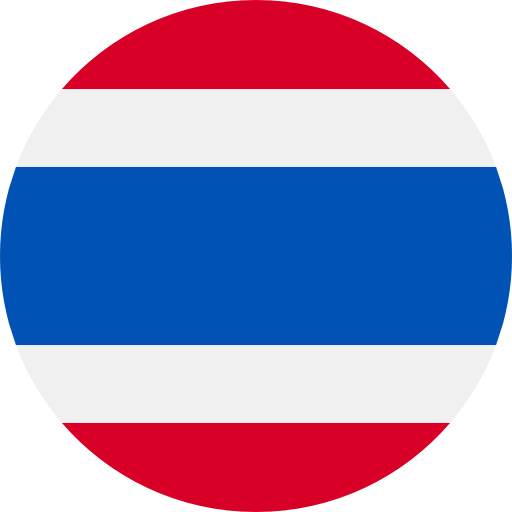 Thai
Thai
 Vietnamese
Vietnamese
 Burmese
Burmese
 Spanish
Spanish
 Portuguese
Portuguese
 Arabic
Arabic
 Russian
Russian
 Chinese
Chinese

